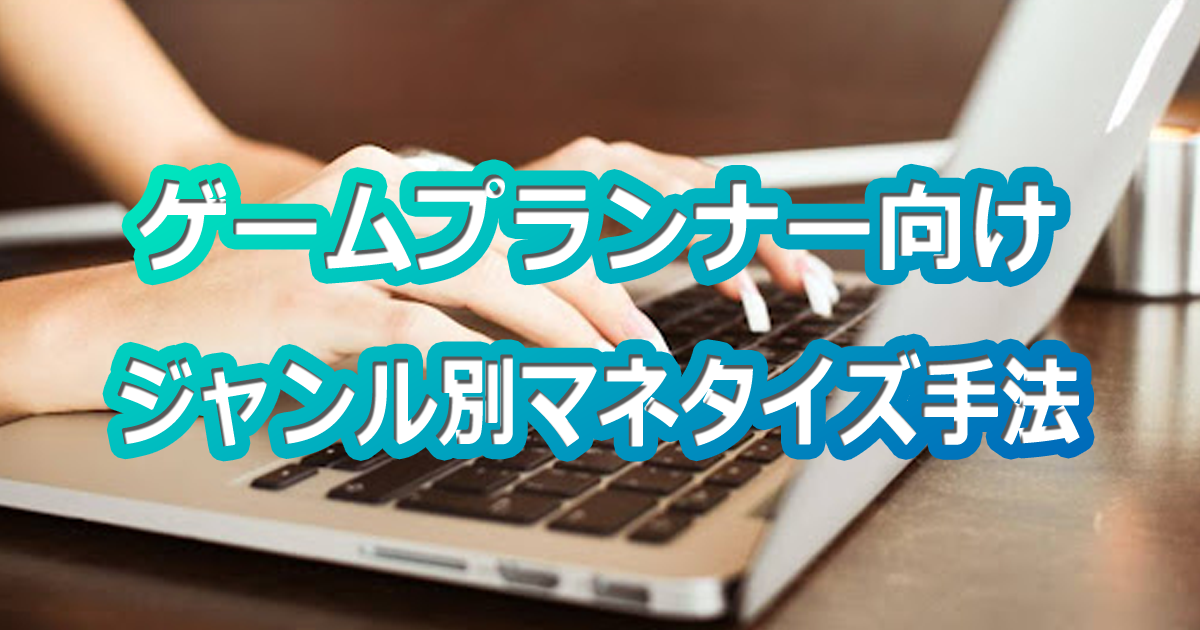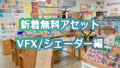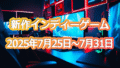ゲーム開発において、「面白さ」と同じくらい重要なのがマネタイズ(収益化)設計です。
とくにゲームプランナーを目指すなら、ガチャや広告、DLCなどの手法を理解したうえで、「自分の企画にどの手法が自然に組み込めるか」を考えることが必須になります。
また、こうした収益設計の知識はインディーゲーム開発者にも有用です。(金なんかいらねーってんなら話は別ですが)
自作ゲームをリリースし、収益を得たいという方も、ジャンルに合ったマネタイズを選べるようになれば、よりプレイヤーに受け入れられやすく、持続可能なゲーム開発が可能になります。
この記事では、ゲームの代表的なマネタイズ手法を7つに分類し、それぞれの仕組み・特徴、ジャンルとの相性(良い/悪い)を一覧化しました。
ゲーム企画や運営設計に関わる方の、実践的な参考資料としてご活用ください。
1. 買い切り(プレミアム販売)
プレイヤーが一度だけお金を払えば、すべてのコンテンツがプレイ可能になる形態。
主に家庭用ゲームやPCのインディー作品で多く採用されている反面、スマホ市場ではやや不利。
1-1. 通常買い切り
従来型のゲームのパッケージ販売や、プラットフォームでのダウンロードなど。
- 向いている:ストーリー重視のアドベンチャー、ローグライク、アクション
- 向いていない:周回前提の育成ゲーム、長期運営型コンテンツ
1-2. チャプター分割販売
前編、中編、後編のような具合に物語を分割して販売する方式。
DLCと違い単体で動作する。
- 向いている:ビジュアルノベル、推理ゲーム、選択型ADV
- 向いていない:PvP中心のソーシャルゲーム
2. DLC(ダウンロードコンテンツ)
ベースゲームに追加コンテンツを有料で提供する形態。
新キャラやマップ、ストーリーなどを後から販売するものであり、これ単体では動作しない。
2-1. 拡張パック型
ゲームの既存コンテンツに追加される、新しい機能、キャラクター、ストーリー、アイテムなどをまとめて販売する方式。
ある程度の高単価になるため、コンテンツ量と価格設定のバランスが最大の肝となる。
- 向いている:RPG、戦略シミュレーション、アクションゲーム
- 向いていない:単発で完結するカジュアルゲーム
2-2. マイクロDLC型
曲データ、スキンデータなど、主にデータ単位で販売する方式。
単価が低いため、課金されやすい。
- 向いている:音ゲー(曲追加)、格ゲー(衣装)、スポーツゲー
- 向いていない:固定ルール・固定構成の作品
3. バトルパス/シーズンパス課金
一定期間のプレイを通じて報酬をアンロックする仕組み。無料と有料の2ライン制が多く、継続プレイを促しやすい。
3-1. 二重ティア型
無料と有料の2ライン制となっており、有料版の豪華報酬をアンロックさせる仕組み。
高ティアになるほど有料版を課金したときの報酬量が増すのが特徴。
- 向いている:PvPアクション、MOBA、バトロワ系
- 向いていない:短編ADV、パズルなどの単発型ゲーム
3-2. 複数グレードあり
バトル向け、育成向け、特定コンテンツ向け、といった具合で複数のバトルパスを並列して設置する仕組み。
プレイヤーは興味のあるコンテンツに関係したバトルパスを選択して課金することができる。
- 向いている:キャラ育成ゲー、ガチャ系RPG
- 向いていない:一本道のストーリー重視ゲーム
4. サブスクリプション(月額課金)
毎月(または週単位)で定額課金し、報酬や特典、ゲーム内サービスを得る方式。
継続プレイを習慣化しやすく、ライト課金層への導入にも使いやすい。
4-1. プレミアムパス型
月額などの定額料金を支払うことで、通常のゲームプレイでは得られない特典や、特定のゲーム内コンテンツの利用権が継続的に得られる課金モデル。ゲームプレイの効率を高めたり、より多くのコンテンツを楽しんだりしてもらい、継続的なエンゲージメントを得るための仕組み。
- 向いている:日課のあるRPG、ログボ強化系
- 向いていない:短命な単発ゲームや非継続作品
4-2. カタログ型(Apple Arcadeなど)
一定金額を払うと色々なゲームが遊び放題になるようなサービス。
SonyやGoogle、Appleなどのプラットフォーマーが行う手法で、一般開発者がこの方式を採用しているのはあまり見たことはない。
- 向いている:複数のカジュアルゲームをまとめたプラットフォーム
- 向いていない:1本で長時間遊ぶタイトル
4-3. 通貨定期支給型
購入金額(投資額)と比較して、定期的にゲーム内通貨をお得に回収できる仕組み。
プレイヤーは中~長期的に見て得かどうかを判断して購入する。
- 向いている:ガチャ中心ゲーム、育成系コンテンツ
- 向いていない:通貨や育成が存在しないゲーム
5. 広告収益(Ad)
ゲームに広告を組み込むことで、無料ユーザーからも収益を得られる手法。
とくに課金率の低いカジュアルゲームとの相性が良い。
5-1. バナー広告
画面の上方や下方にバナー画像を出す仕組み。
画面の一部を占有するためUXが悪くなりやすい上に、低単価。
- 向いている:放置系、パズル系、カジュアルゲーム
- 向いていない:没入感の重要なADVやホラーゲーム
5-2. インタースティシャル広告
画面の切り替わりやゲームのリトライ時などに挟まる全画面広告。
単純に面積が広いため、高い注目度と高いクリック率になる傾向がある。
- 向いている:リトライ型スコアアタックゲー
- 向いていない:操作に集中が必要な音ゲーやアクション
5-3. リワード広告
ユーザーが動画広告の視聴や特定のアクションを行うと、ゲーム内報酬が得られる仕組みの広告。
ユーザー自身が報酬のために広告を選択する「プル型」の広告モデルで、広告への拒否感が低く、プレイヤーのエンゲージメントを高めながらゲームの収益化を図ることができる。
- 向いている:ガチャ補助、スタミナ回復、報酬ブースト
- 向いていない:1回完結型のストーリーゲーム
6. ガチャ(ランダム課金)
ランダムにアイテムやキャラクターを排出する方式。
収益性は高いが、法による規制や賭博性への配慮が求められる。
6-1. キャラガチャ
キャラクターがランダムで手に入る、一番スタンダードな方式。
キャラを手に入れれば直接的に強くなっていくため、「Pay to Win方式」と呼ばれる。
- 向いている:キャラ収集が主目的のゲーム、美少女RPG
- 向いていない:公平性が重視される対戦ゲーム
6-2. 装備ガチャ
キャラクターに装備させるアイテムが手に入る方式。
同じく「Pay to Win方式」だが、キャラガチャと比べて魅力が劣る場合が多い。
なお、キャラや装備など異なる種類のアイテムを同じガチャで排出させるものを、俗に「闇鍋ガチャ」と呼ぶ。
- 向いている:MMO、ハクスラ系
- 向いていない:完全スキル型ゲーム(格ゲーなど)
6-3. スキンガチャ
主にキャラの見た目のみを変化させるアイテムが手に入る方式。
強さや攻略性などには関与しないため、「Pay to Fun方式」と呼ばれる。承認欲求とも関係が深い。
- 向いている:バトロワ、観戦型PvP
- 向いていない:見た目を重視しないドット絵作品など
7. アイテム課金(都度課金)
必要なアイテムを都度購入する方式。
ガチャのようなランダム性がなく、自然な課金設計をしやすい。
7-1. 通貨販売
一定のレートでゲーム内通貨を販売する方式。
ゲーム内通貨はゲーム内で様々な用途に使うことができる。
- 向いている:育成、建築、強化があるゲーム
- 向いていない:アクションやパズルのようなスキル特化型
7-2. 時短アイテム
ゲーム内の待機時間や回復時間などを短縮するために使用するアイテムを販売する。
電子書籍アプリなどでも同様の仕組みが利用されている。
- 向いている:建国ゲー、クラフト系
- 向いていない:そもそものセッションが短いゲーム
7-3. スタミナ回復
ここでいうスタミナとは、ゲームを遊ぶために必要な数値やアイテムのこと。
通常は時間経過で蓄積していくが、これを課金で回復させる。(時短アイテムのバリエーション)
- 向いている:周回型RPG、イベント周回ゲーム
- 向いていない:スタミナで進行を制限する必要のないゲーム
7-4. 装飾アイテム販売
見た目を飾るアイテムを販売する方式。
自己満足のほか、スキンガチャ同様に承認欲求を満たす手段の一つとして購入していく。
- 向いている:アバター要素、メタバース系、箱庭系
- 向いていない:他ユーザーとのコミュニケーションが無いゲーム
その他の手法
例えば、ライブサービス型ゲームにおける「イベント課金」のような手法がある。
期間限定イベントに合わせて販売される特別アイテム・ガチャ・参加券などを通じて収益を得る方式で、ライブサービス型運営の中心的な収益源となる。
手法としては紹介した1~7の合わせ技に過ぎない。
まとめ:相性の良さ=収益の自然さ
マネタイズは「儲かりそうな方法を入れる」ものではなく、そのゲームの遊び方に自然になじむ形で設計されているかが非常に重要です。
ユーザーが納得してお金を払ってくれる仕組みを作れれば、開発者にもユーザーにも幸せな運営が成立します。
逆にマネタイズ手法ありきで考えたゲームは、市場に受け入れられない可能性が高いと思います。
プランナー志望の方はもちろん、インディー開発者の方も、このマネタイズ分類を一度ゲーム設計に照らしてみてください。
企画の完成度がグッと高まり、継続的なリリースや運営の土台になるはずです。