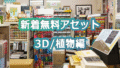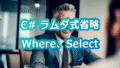ゲーム内での殺人行為の規制、という話では全くなく、「ゲーム(自体)を殺すな」という運動の話です。このゲーム保存運動「Stop Killing Games」が、欧州で100万件超の署名を達成しました。
「買ったゲームが消える(サ終する)」ことに対する消費者と文化保護の運動が、法制化の第一歩へと進んでいます。
ゲームが「買い切り」じゃなくなる時代に抗う運動
―なぜ「Stop Killing Games」は生まれたのか?
ここ十数年で、ゲームの“所有”のあり方は劇的に変化しました。
かつては、パッケージを購入すればいつでも何度でも遊べる「買い切り」型が当たり前でした。
しかし現在では、オンライン認証やサーバー依存型の「サービスとしてのゲーム(Games as a Service)」が主流となり、
“所有しているはずのゲーム”でさえ、突然プレイできなくなる時代に突入しています。
Ubisoft『The Crew』サーバー停止(2024年)
2024年4月、Ubisoftが2014年発売のレーシングゲーム『The Crew』の全サーバーを停止。
このタイトルはオンライン専用で、サーバーが閉じられた瞬間、購入済みプレイヤーすら一切プレイ不能になりました。
- 「返金対応なし」
- 「オフラインモードなし」
- 「後継作への引き継ぎ不可」
この事件が、「Stop Killing Games」の直接の引き金となりました。
日本でもフルプライスで発売したにも関わらず短期間でサ終してしまった「BABYLON’S FALL」が記憶に新しいです。
そして「Stop Killing Games」へ・・・
2024年、Ubisoftのオンライン専用ゲーム『The Crew』のサーバー停止がきっかけで始まったこのキャンペーンは、YouTuber・ロス・スコット氏によって発起されました。
目的は明確でシンプル。
「ゲームを購入したプレイヤーが、そのゲームを将来にわたってプレイできる権利を守ること」。
この運動の裏には、ゲームを文化財とみなす視点もあります。
映画や音楽がアーカイブされるように、ゲームにも同じ権利と責任が必要ではないか――。
ゲームを単なる“商品”ではなく、“表現”や“文化”としてとらえるなら、「サービス終了=文化の抹消」となりかねません。
これは単なる保存運動ではなく、文化遺産の保護、消費者権利の訴求でもあります。
EU署名数100万件突破で制度化へ前進
2025年7月、EU市民イニシアチブ(ECI)の枠組みに基づき、
「Stop Killing Games」キャンペーンは100万件超の署名を突破。
これにより、欧州委員会での審査対象となる資格を取得しました。
運動のステップ(EUプロセス)
- 署名検証:国別に正当性を確認
- 欧州委員会協議:1か月以内に開催
- 欧州議会公聴会:最大3か月以内
- 欧州委員会対応表明:6か月以内(法案化の可能性も)
※7/20追記
さらに7月20日時点で署名数は140万件を突破。仮に一部署名が無効でも、十分な有効数を満たしていると見られます。
この件に関する業界と政治の反応は?
- Ubisoft CEOの見解
「すべてのゲームに永続サポートを保証することはできない。だが、予告期間を設けるなど、対応改善中」とコメントしました。 - EU議員
ルーマニアのステファヌタ議員はキャンペーンを直接支持し、「購入したゲームは買った人のもの」という価値観を訴えました。 - ゲーム業界団体
業界団体「Video Games Europe」は、「プライベートサーバーの許可やオフライン化義務は開発者の自由を損なう」と反論している模様。 - KuroMikanの反応(←
保存はいいけど、みんなサ終タイトルのオフラインアプリ遊んでる?やってなくね?
今後のポイント
- 欧州委員会の正式対応(公聴会・法案起草の可否)
- 企業側がプライベートサーバー開放・オフライン対応を進めるか
- 欧州以外(米国、日本など)への波及と規制の国際化
まとめ:私たちの買ったゲームは“誰のもの”か
「Stop Killing Games」は、デジタル時代における“所有”の意味を問い直すキャンペーンです。
プラットフォームや個々のサービスが終了すると消えてしまうゲームたち。これらを保存したい気持ちはよくわかります。
KuroMikanはとりわけ影響を受けやすいスマホゲーム開発の現場にいるわけですが、このキャンペーンの結果次第では今のライブサービス型のゲーム設計そのものに影響を与える可能性すらあります。
2025年の今、ゲームの“終活”をどう設計するか――
それが、これからのゲーム業界にとって最大のテーマになるかもしれません。
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]