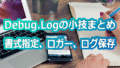近年、ゲーム業界では「新作が多すぎるのではないか」という議論が強まっています。
2025年9月には Bloomberg の Jason Schreier 氏が「現在はゲームが多すぎる(供給過多)」と発言し、世界的に大きな話題となりました。
開発ツールや配信プラットフォームの普及によって、インディーからAAAまで膨大な数のタイトルが同時期にリリースされ、消費者がすべてを追い切れない状況になりつつあるのです。
海外メディアの論調
この問題は Bloomerg だけでなく、複数のメディアが取り上げています。
- Financial Times は「ゲームの超過剰時代をどう生き抜くか」をテーマに、Steamでの年間数万本リリースを背景に分析。
- Reuters は Embracer Group CEO の発言を引用し、「市場が過密すぎて小規模タイトルが発売時期の調整を迫られている」と報じました。
- Medium や LinkedIn ニュース でも、発見性の難しさや開発者にかかる競争圧力が強調されています。
- 国内では 東洋経済 や 電ファミニコゲーマー が、供給過多と競争激化を背景に「運営力の重要性」や「新規参入の困難さ」を指摘しています。
こうした論調から見えてくるのは、単なる「本数が多い」ではなく、消費者の可処分時間・注目の奪い合いが深刻化しているという構造的な課題です。では、なぜこのような構造が生まれてしまったのでしょうか。
背景にはまず、開発環境の進化と開発費の下限の低下があります。Unity や Unreal Engine といったゲームエンジンの普及により、小規模なチームや個人でも家庭用機やPC向けに本格的なタイトルを制作できるようになりました。さらに AI や生成ツールの活用によって、開発スピードは一層加速しています。
次に、流通の門番が弱体化したことが挙げられます。かつてはパッケージ流通や大手パブリッシャーを通さなければ市場に出られませんでしたが、現在は Steam、App Store、Google Play、itch.io、BOOTH などのデジタルプラットフォームを通じて、誰でも世界中に作品を公開できます。結果として、年間数万本規模の新作が同じ市場で同時に競合する事態が常態化しました。
そして何より、消費者の可処分時間は有限であるという根本的な制約があります。サブスクリプションサービスやソーシャルメディア、動画配信など、ゲーム以外の娯楽も競合する中で、ユーザーが実際に遊べるタイトルはごく一部に限られます。そのため、どれだけ選択肢が増えても、注目の奪い合いは激しくなる一方です。
このように、開発・流通のハードルが下がり供給が爆発的に増えた一方で、需要側の「時間」という資源は拡張できないことが、市場飽和の構造的な原因だと考えられます。
とあるSteamユーザーが4万本以上のゲームを所持
象徴的なニュースとして、2025年9月には Steamの所持ゲーム数が4万本を超えたユーザー が現れ、コミュニティで話題になりました。膨大なゲームが容易に入手可能になった現代を示す一例であり、供給過多の状況を象徴する出来事とも言えるでしょう。
市場飽和がもたらす影響
ゲームの供給過多は、完成度の高いタイトルであっても注目されずに埋もれてしまうリスクを高めています。発売スケジュールが混雑し、人気作との競合を避けるために発売延期を余儀なくされるケースも少なくありません。
その結果、開発者にとっては売上予測が立てにくく、資金回収の見通しが不透明になるなど、リスクが増大しています。
まとめ:どうやってゲームを見つけてもらうか
「ゲームが多すぎる問題」は、単なるユーザーの選択肢拡大にとどまらず、開発者・パブリッシャー・販売プラットフォームすべてに影響を及ぼしています。
Steamで数万本単位のゲームが存在し、1ユーザーが4万本ものタイトルを所有する時代においては、「どのゲームを遊んでもらうか」よりも「どうやって見つけてもらうか」が重要課題となっています。
KuroMikanもこの件には課題感を持っており、そのための活動として「新作インディーゲーム情報」の記事を作成しています。(たまに配信タイミングが遅れますが……)
東京ゲームショウ2025や各種デジタルショウケースでも新作が次々発表される中、今後の業界は「供給過多」とどう向き合うのか、その動向が注目されます。
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]