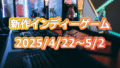近年のゲーム市場は大きく分けて、
企業が制作する「AAA級タイトル」と、個人や小規模チームが制作する「インディーゲーム」が存在します。
潤沢な資金と優秀な開発者を抱える大企業が、数十億円、時には数百億円もの予算をかけて開発するゲームは「AAA(トリプルエー)級タイトル」と呼ばれます(規模によっては「AA級」と表現されることもあります)。
これらのゲームは、PS5やSteamなどのハイエンドなプラットフォームだけでなく、近年ではスマートフォンでも同様のスケールで開発されるようになっています。
有名な例では、『原神』が400人以上の開発体制で制作されたと開発者の間で話題になりました。
一方で、個人や少人数のチームが制作する「インディーゲーム」というジャンルもあります。
インディーゲームでは、大手企業ではリスクが高くて手を出しにくいような独創的なジャンルや、過去作品の精神的続編のような作品が多く見られます。
売上規模こそ大企業の作品に及びませんが、インディーゲームはAAAタイトルと「食い合う」ことなく、独立した市場として共存しています。
個人でゲーム制作に挑戦するなら、現実的にはインディーゲーム一択と言えるでしょう。
ゲームづくりのための準備
AAAタイトルの場合
どこの企業かは伏せますが、あくまで業界一般のイメージとしてご覧ください。
新しいゲームを作るには、まず企画書(提案書)を作成します。
この企画書には以下のような情報が盛り込まれます:
- 現在の市場分析
- ターゲットユーザー層
- ゲーム内容の概要
- 収益化ポイント(マネタイズ設計)
- 座組(共同開発企業の構成)
- 開発予算
- 想定KPI(売上・DAUなど)
- 開発スケジュール
この情報をすべて一人で用意するのは不可能に近いため、マーケティング部門に市場データを依頼したり、デザイナーにラフ案を描いてもらったり、外注先候補に声をかけたり、上司に根回しをしたりと、まさに「元気玉」的に人の力を集めて進めます。
企業としては巨額の投資をする以上、経営陣が納得できない資料ではプロジェクトは通りません。せっかく集めた元気玉も、方向がズレていたら無効です。
奇跡的に企画が通ったとしても、その後は:
- 仕様書の作成
- 開発メンバーのアサイン
- 開発体制の構築
- 会議体や報告フローの整備
- チーム内のトラブル対応
- 蒸発したメンバーのリプレース
- 懇親会のセッティング
- その懇親会で鞄を盗まれる(←実話)
…などなど、想像以上に雑務が多いのが現実です。
「純粋にゲームを作りたいだけなんだよなぁ」という人にとっては、正直しんどい工程です。
企画を立てた人は、プロデューサーやプロジェクトマネージャーになることがほとんどで、
「ゲームを作りたいのに作る時間がない」状態に陥ることも少なくありません。
インディーゲームの場合
個人で取り組むインディーゲームでは、巨大な元気玉は必要ありません。
「必要なもの」を揃えて、あとは作るだけです。
▶ 必要なもの
- パソコン
スマホゲーム開発の場合、iOS向けにリリースしたいならmacOSが必須です。 - スマートフォン
動作確認用。Android端末では「開発者向けオプション」の有効化を忘れずに。 - Unity
Unityは、ユニティ・テクノロジーズ社が提供する無料で使えるゲームエンジンです。
ステージやキャラなどの要素を視覚的に操作できるため、難解な3Dや物理演算の知識がなくても開発できます。
また、iOS・Android・PC・PS5・Nintendo Switchなど、幅広いプラットフォームに対応しています。 - Unreal Engine
Epic Games社が提供する高品質ゲームエンジン。
映像美に優れており、建築や映像制作、VRなどにも使用されています。
KuroMikanが関わった作品では、ゲーム本体はUnity、ムービー部分はUnreal Engineで制作した例もあります。 - 企画書(仕様書)
規模に応じて、最低限「どんなゲームをいつまでに作るか」は決めておくべきです。
壮大すぎる内容は避けましょう。
KuroMikanは「ゲーム開発の経験値は、完成と公開によって得られる」と考えています。
完成までに時間がかかるゲームは、経験値効率が悪く、挫折の原因になります。
「エターナる(=永遠に完成しない)」という言葉を忘れずに!
ゲームづくりの基本を理解する
企画書を作る
「こんなゲームを、いつまでに作ります」──最初はこのレベルで十分です。
これすら作らない状態だと確実に迷走するので、必ず「これから作るもの」について書き出しましょう。
制作する
スケジュールと企画が決まったら、まずゲームの核となる「インゲーム」部分から作ります。
タイトル画面やメニューなどの装飾要素は、ゲームの面白さが見えてからでもOK。
グラフィックにこだわりすぎると進まなくなるので、最初はシンプルな見た目で構いません。
レベルデザインする
あまり語られませんが、実は非常に重要な工程です。
例えばRPGで、最初の草原に強すぎるドラゴンが出てきたら、誰もが「クソゲー!」と叫んで離脱するでしょう。そこでこのようなストーリーにします。
- 弱いスライムと戦って基本ルールを学ぶ
- 少し強い敵が出る洞窟で武具や魔法の重要性を学ぶ
- 洞窟を抜けた先でさらに強い敵が現れるが、手に入れた装備で乗り越えられる
このように、
- ①でルールを学び、
- ②で試行錯誤し、
- ③で成長の実感と達成感を得る
という構造が、プレイヤー体験の満足度を高めます。
「ギリギリ勝てるかどうか」の緊張感が、ゲームを最も面白くする要素のひとつです。
デバッグする
ゲームを自分でプレイし、不具合を洗い出します。
「敵に弾が当たってるのにダメージが入らない」など、想定外の挙動がよくあります。
また、開発者自身は「知っている」ので決められた手順で操作してしまいがちですが、不具合は「決められた手順以外」によく潜んでいます。こういうときはモンキーテスト(事前に定められた手順や仕様を無視し、思いつきやランダムな操作をシステムに与えて、予期せぬ不具合やエラーを発見する手法)が有効だったりします。
とても大変ですが、ここは丁寧に修正していきましょう。
リリースする
ゲームが完成したらすぐ公開、とはいきません。公開に必要な情報(スクリーンショットや紹介文など)を用意しましょう。
情報が揃ったら、目的のプラットフォームに公開を申請します。
- PCゲームなら → STEAM に申請(登録は全て英語!難易度高)
- スマホゲームなら → App Store / Google Play に申請
- Webゲームなら → 各種フリーゲーム投稿サイトに登録
最後に
ここまで読んで「自分もゲームを作ってみたい!」と思った方は、ぜひUnityでの開発を始めてみましょう。
最初のうちは、ネット上の断片的な情報を追うより、初心者向けの書籍を一冊買って「写経(=サンプルコードの丸写し)」するのがおすすめです。
KuroMikanも5冊以上写経し、そこからサンプルゲームを魔改造しながらオリジナル作品を作れるようになりました。
とにかく手を動かす。これに尽きます!